こんにちは!
まだまだ厳しい暑さが続いていますね。外に出るのも億劫になりがちですが、こんな時こそ落語で涼んでみませんか?
今回ご紹介するのは、夏の気分をたっぷり味わえる噺『青菜(あおな)』です。
目次
1.あらすじ
- 夏の涼やかなもてなし ある暑い日の昼下がり、植木屋が屋敷で仕事をしていると、主人の旦那が庭に水をまき、涼しくしてくれます。さらに、冷えた「柳蔭」と「鯉の洗い」でもてなします。
- 粋な言葉と勘違い 旦那が奥さんと隠し言葉で会話をすると、植木屋はその粋なやりとりに感心します。
- 大失敗の鸚鵡返し 自宅に戻り、早速この洒落を真似しようとします。植木屋は奥さんに「青菜はあるか?」と尋ねる役をやらせますが、戻ってきた奥さんが「鞍馬から牛若丸が出でまして、名を九郎判官義経・・・・・・」と、なんと最後まで答えてしまい、植木屋は「義経、義経」と言えなくなってしまいます。とっさに飛び出した言葉は「弁慶にしておきない」という、なんとも滑稽なオチです。
2.『青菜』の魅力を紹介
■暑い夏でも、情景描写で「涼」がとれる
『青菜』は、粋な旦那と、少しおっちょこちょいな植木屋のやりとりが楽しい、夏の風物詩のような噺です。登場人物の会話や情景描写が非常に細かく、まるで目の前にその風景が浮かび上がるようです。
■前半の涼しい夏と、後半の暑い夏の対比が面白い
この噺の魅力は、なんといっても「言葉の面白さ」にあります。噺の前半では、夏の昼下がりの涼やかな情景が描かれ、後半では、旦那の粋な言葉を真似ようとして失敗する植木屋の姿が、ユーモラスに描かれます。この前半と後半の「暑さの対比」が、この噺の大きな見どころです。
■ユーモアな言葉遊び
ある夏の暑い日、植木屋が仕事で屋敷を訪れると、旦那は冷たい「柳蔭」と「鯉の洗い」でもてなします。 植木屋の前で、旦那が奥さんに「青菜があるか?」と尋ねます。すると奥さんは奥から戻ってきて「鞍馬から牛若丸が出でまして、名を九郎判官」と伝えます。 これに対して、旦那は「義経、義経」と答えるのです。
実はこのやりとりは、周囲の植木屋にはわからないようにするための隠し言葉。 奥さんの「名を九郎判官」は「名(菜)は食ろうた(食った)」という言葉を、旦那の「義経、義経」は「よし、よし」という言葉をそれぞれ表していました。
植木屋は、自分にはわからない粋な言葉遊びに少し恥ずかしくなった旦那の姿を見て、反面、その粋なやりとりに感心します。
■落語を知らなくても、思わず笑ってしまう
『青菜』は、難しい言葉や時代背景を知らなくても、登場人物のやりとりの面白さだけで十分に楽しめます。旦那の粋な計らいと、それを真似て失敗する植木屋の姿に、思わず笑みがこぼれてしまうでしょう。
最後に
いかがでしたか?
「落語は難しそう…」と感じていた方も、ぜひ一度『青菜(あおな)』を聞いてみてください。落語の面白さや奥深さを知る、いいきっかけになるはずです。
この残暑、落語で涼やかな気分を味わってみませんか?
これからも、落語の魅力をもっと発信していきますので、どうぞよろしくお願いします!

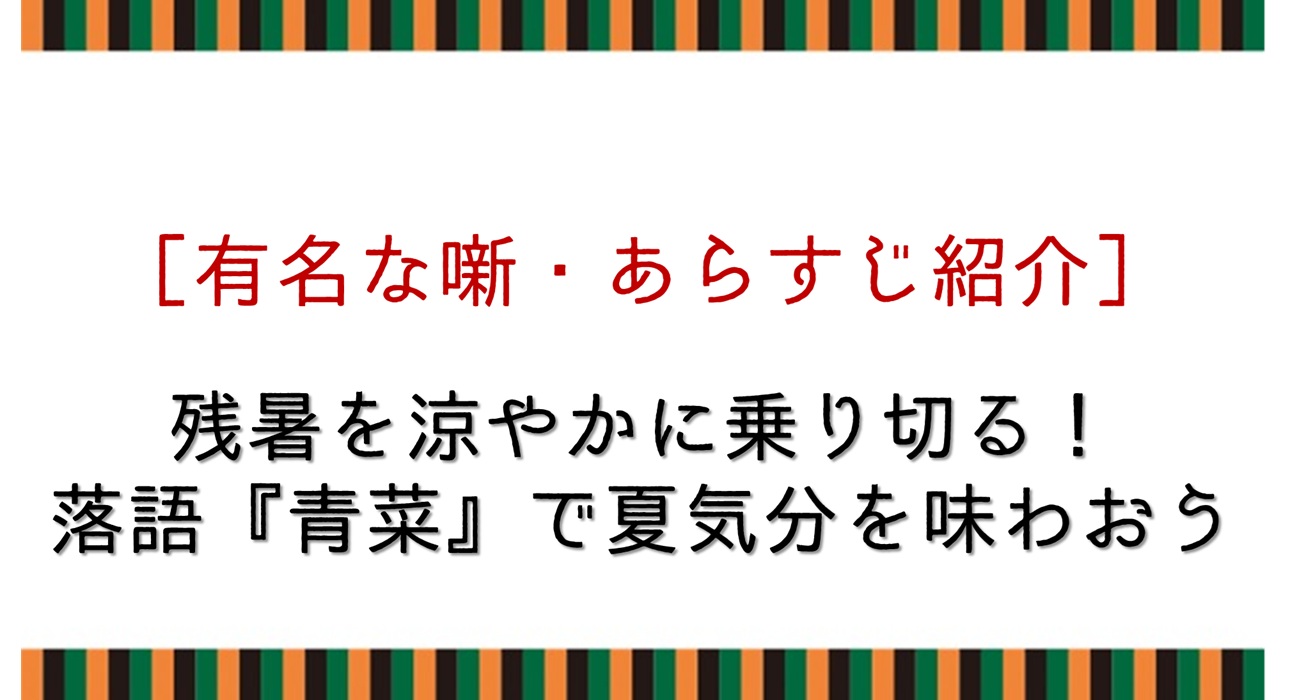

コメント